
欧州に学ぶ緩やかな変革
烏取大学教授 上田 茂 日本海上起重技術協会の欧州調査の報告書を取りまとめを行っていた最中の3月17日、読売新聞のコラムにポール・サミュエルソン博士の論文が掲載された。その内容は、日本経済の混迷の度合いを記述したもので、その状況をこう書いている。すなわち、日本がその進路の分岐点に差しかかったのは、1990年代ころであり、症状としては土地バブルと株式バブルが突然はじけたまっていたうみが出て、以来、日本経済の低迷は主要先進国のどこよりも深刻でありかつ悪性であると指摘している。そして、その原因は、”おごり”であると、明快に断言している。かつて欧米の経済学者は、「日本式の新しいコンセンサスによる管理方式」に注目し、日本企業は長期的視野に立って物事を判断する豊富な資力をもっていると、みなした。しかし、一方では、「堕落した西欧」、「英国病」などという蔑視になって表れ、ある意味では傲慢なところさえみられたと評している。 資源のない我が国が、戦後の荒廃から立ち上がり、今日の繁栄を享受するに至ったのは、自ら世界の工場を任じ、軽工業、重工業、先端産業などの分野で、世界に先掛けて、高品質でかつ安価な製晶を生産できる産業基盤を整備し、全国民が一丸となって努力したからにほかならない。鉄鋼、自動車、オートバイ、電子機器、音響機器、カメラ、などいずれをとっても、日本製品の品質の良さと安さには定評があった。欧州へ旅行する時には、ホンダ、スズキ、カワサキなどと称すれば、パスポートコントロールも問題なくクリアできるなどと、まことしやかにささやかれたものである。しかし、いま我々の周辺には、東南アジアの製品が溢れている。とくに、中国、マレーシア、タイなどの製品が目につく。かつて日本製品が世界を席捲していたときと全くおなじ現象が、アジアの隣国によってなされているのである。 この度、欧州を訪れ、これらの国々が生き生きとして見えた。ロッテルダム港の沖合で展開されているほどの規模の工事は、今日、我が国でも見ることができない。その後、今年の1月にアントワープ港を訪問したが、同じく大規模な港湾開発を行なっているのを目の当たりにした。ロッテルダム港が埋立てであるのに対し、アントワープ港は掘り込み港湾である。前者は、海域の自然環境保護を重視して、むかしながらの巻きだし工法で護岸整備をしているが、後者は農耕地を掘り込むため、農民の移転対策に苦慮しながら整備を進めている。じつは、この両港は隣合う、オランダ王国と、ベルギー王国の唯一の主要港湾であり、かつスイス、オーストリアなどの内陸の諸国への玄関の役割を担っている。日本の東京と横浜、または、大阪と神戸程度の距離にあって、競い合っているのである。日本と違って、工業港とか商港などといった区分は見られず、それらの機能が混然一体となっている。道路、鉄道による輸送の効率的な分担 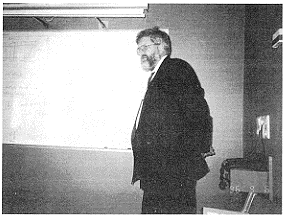
前ページ 目次へ 次ページ
|

|